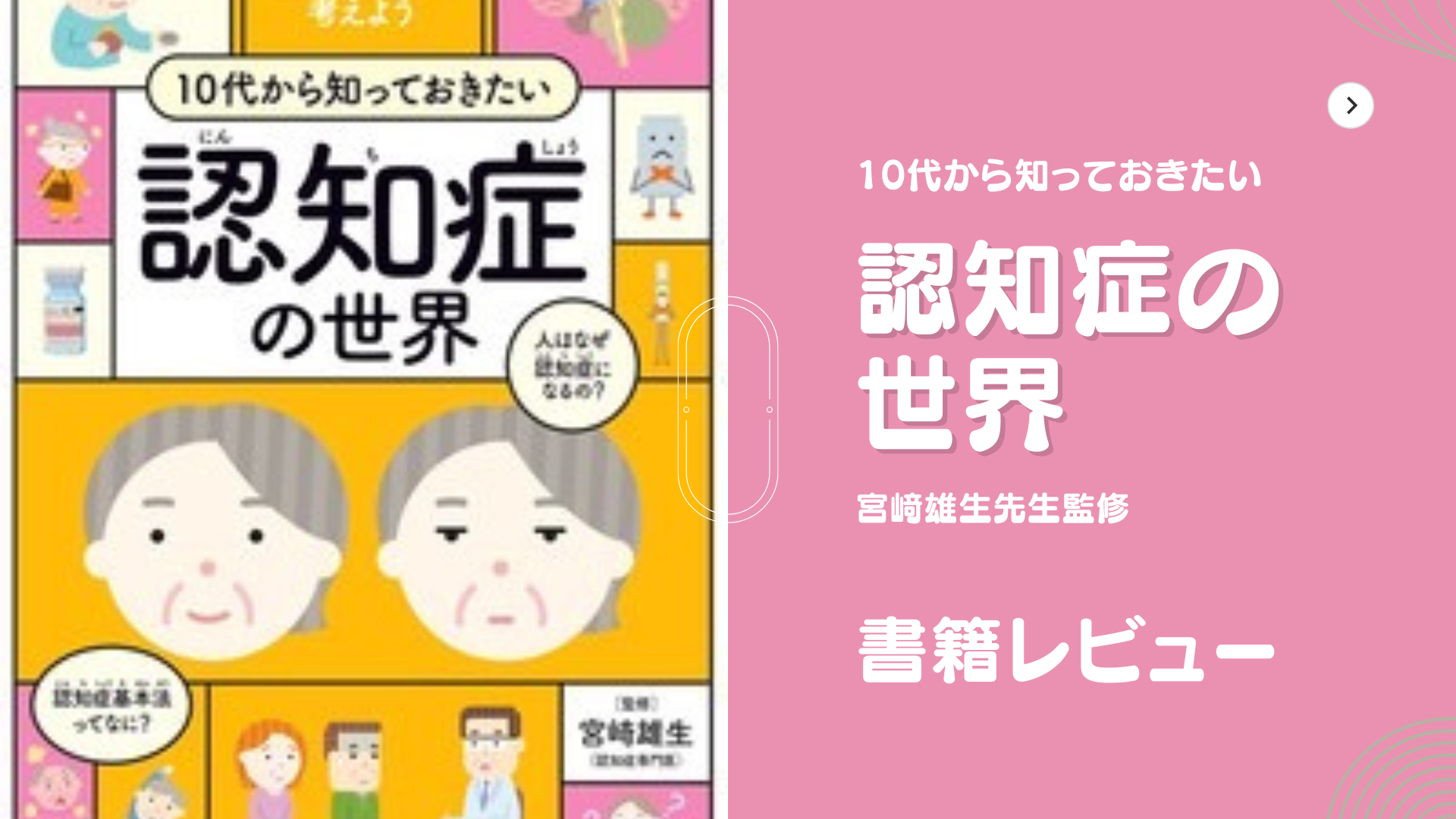はじめに
「認知症」という言葉を聞いて、どんなイメージが浮かびますか?
高齢の人の病気? 自分にはまだ関係ないこと? もしかしたら、「ちょっと難しそう」と思う人もいるかもしれません。
でも今、認知症を“10代から知っておくこと”には、大きな意味があります。
それは、これからの社会で「ともに生きる力」を身につけるということだからです。
今回ご紹介するのは、**『10代から知っておきたい、認知症の世界』(宮﨑雄生 監修)**という一冊。
副題は「共生社会を考えよう」。認知症を“学ぶ”だけでなく、“ともに生きる”という視点から考えるきっかけをくれる、温かい本です。
本書の概要と特徴
この本は、10代の読者にもわかりやすいように、やさしい言葉と親しみやすいイラスト、図解で構成されています。
内容は認知症の基本的な知識にとどまらず、
- どんな症状があるのか
- 周りの人はどう接したらよいのか
- 認知症のある方の感じている世界とは?
といった、「心に寄りそう視点」が随所に盛り込まれています。
また、現場で働く人の声、当事者の体験談なども掲載されており、「わたしにもできることがある」と気づかせてくれる一冊です。
印象に残った4つの内容
1:認知症は「遠い未来」ではなく「身近な現実」
認知症は高齢の人だけの話ではありません。
働き盛りに発症する「若年性認知症」や、身近な祖父母の変化などを通じて、私たちの暮らしとつながっています。
この本では、認知症を「他人ごと」としてではなく、「自分のまわりにも起こりうること」として紹介しており、どの世代の人にも関係のあるテーマであることを実感させてくれます。
2:「認知症になったらどう感じるの?」をやさしく解説
本書では、認知症のある人が「どんなふうに世界を感じているのか」を、イラストとやさしい文章で丁寧に伝えています。
たとえば、次のような症状があります:
- 記憶障害:最近の出来事を思い出せない
- 徘徊(はいかい):自分がどこにいるかわからなくなってしまう
- 物取られ妄想:大切なものがなくなり「誰かが取った」と思ってしまう
- 視空間認知障害:ものの位置や空間がわからなくなる
- 遂行機能障害:料理や準備など、順序立てて行うことが難しくなる
- 失語・失行:言葉が出てこなかったり、道具の使い方がわからなくなる
- 社会的認知障害:相手の気持ちや表情がわかりにくくなる
それぞれの症状について、日常生活の例を交えながら、「どうしてそんなことが起こるのか」「本人はどんな気持ちか」が解説されており、理解がぐっと深まります。
行動の背景にある“心の動き”に目を向けることの大切さを、やさしく教えてくれる章です。
3:「知識」より「まなざし」が大切
本書が伝えるもう一つのメッセージは、「認知症をどう見るか」という視点。
知識があっても、“相手をどう見ているか”によって、関わり方は大きく変わります。
たとえば、困っているように見えても、そこには「一生懸命なんとかしようとする努力」があるかもしれません。
本書では、認知症のある人を「できない人」として見るのではなく、「できることをいっしょに見つけていく存在」として描いています。
上からの支援ではなく、「となりに立って、ともに歩む」という関係性の大切さに気づかせてくれます。
4:できることに目を向ける
認知症になったからといって、すべてが「できなくなる」わけではありません。
むしろ、「今もできること」「その人らしさ」に目を向けることが大切です。
本書では、認知症のある人が「買い物を楽しむ」「話を聞くのが得意」「手仕事をするのが好き」といった姿も紹介されています。
支援するというより、「一緒にできることを楽しむ」という関わり方が、本人の尊厳を守り、周りとの温かいつながりを生み出していくのです。
「共生社会」って何? 〜本書から見えてくる未来像〜
副題にもある「共生社会(きょうせいしゃかい)」とは、「違いを認め合い、誰もが安心して暮らせる社会」のこと。
認知症のある人、障がいのある人、子ども、高齢者、外国人…さまざまな背景をもつ人たちが、ともに暮らせる未来をどうつくるかが問われています。
本書は、そうした共生社会を考える入り口として、若い人にも無理なく届くようにつくられており、「まずは知ること」からはじめようと語りかけてくれます。
🌱豆知識:認知症基本法って知ってる?
2023年、日本で「認知症基本法」が成立しました。
正式には「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」といい、認知症のある人が安心して暮らせる社会を目指すための基本方針が定められています。
この法律では、
- 国や自治体が支援を進める責任があること
- 認知症のある本人の声を大切にすること
- 地域や学校での理解促進を行うこと
などが明記されています。
本書でもこの法律についてわかりやすく紹介されており、制度面にも関心を持つきっかけになるでしょう。
こんな人に読んでほしい
- 学校で「福祉」や「社会の課題」について考えている中高生
- 地域活動やボランティアに関心がある方
- 家族に認知症のある人がいる方
- 「やさしい社会をつくりたい」と感じているすべての人へ
おわりに 〜「知ること」が共生の第一歩〜
認知症は「特別な人の話」ではなく、これからの社会で誰もが関わる可能性のあるテーマです。
そして、知ること・想像すること・ともに生きることは、誰でも今すぐ始められます。
『10代から知っておきたい、認知症の世界』は、優しさと気づきに満ちた一冊です。
この本をきっかけに、自分と誰かをつなぐ「共生のまなざし」を育てていきませんか?
📚書籍情報
- 書名:10代から知っておきたい、認知症の世界
- 監修:宮﨑 雄生
- 出版社:旬報社
- 発行年:2023年
- ISBN:978-4845117686